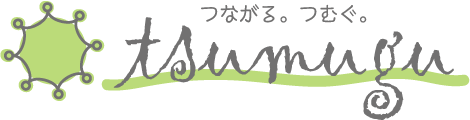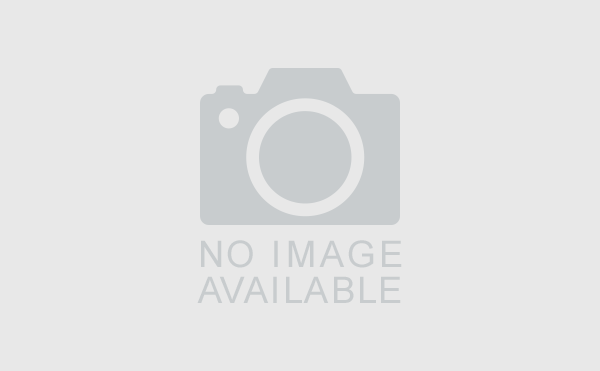ITとICT。間に入る「C」とは?
パソコン関連の用語の中に「IT」という言葉があります。
ITとは、Information Technologyの略称。「情報」を得る、加工する、保存する、伝えるといった技術を総称してこう呼んでいます。
少し前までは、ある特定の人たちだけがその技術を使い、その恩恵を受けていましたが、今では情報を伝えるための技術全般が向上し、わたしたち一般の人にも使いやすく整備されていっています。
このITはわたしたちの生活の中に根付き、目には見えづらいですが、恩恵を与えています。
ただ、ITというと無機質であるような、顔が見えないそんなイメージを持たれているかもしれません。
ですが、ITを使っているのは人間です。パソコンでインターネットに接続している先にも私たちと同じように人間が存在しています。
人と人とをつなぐ、それがITです。
そして、こんな言葉も登場しました。「ICT」です。
Information and Communication Technology、先ほど書いたITの間に「C」が入ることで、通信技術を使ったコミュケーションと表すことができます。
技術だけが発達しても、それを使うのは人間。わたしたちです。
わたしたちがその技術を使うことでコミュニケーションを円滑にしたり密にしたりすること。
人が人とつなげるためにITという技術を使う。
今の時代、インターネットに接続できる端末は増えました。インターネットの速度はどんどん向上していきます。
速度が向上すれば、多くの情報を一度に送りあうことができるようになります。
ただ、問題があるとすればほとんどが文字情報の送り合い。文字というのは気持ちを込めて送ったとしても、受け取り方は相手次第。
顔を合わせて話をすれば、相手の表情や声質で相手の感情を想像できますが、文字だけではなかなか伝わりにくい。
文字だけのやり取りで思いを伝えるのは難しい。
それを理解しているだけでも誤解が生まれる確率は減らせるのではないかと思います。
技術はどんどん進化します。
でも、だからといってそれらをすべて取り入れる必要はありません。
なぜなら、技術はたくさんあっても、必要のない技術も世の中には存在するからです。
いろいろな技術があります。サービスがあります。
それらがどんなものかを知る。
知ることからまずは始めて。そのうえで必要かを判断する、選択する。
これから先のICTはこの、選択できる力を養うことだと管理人は思います。